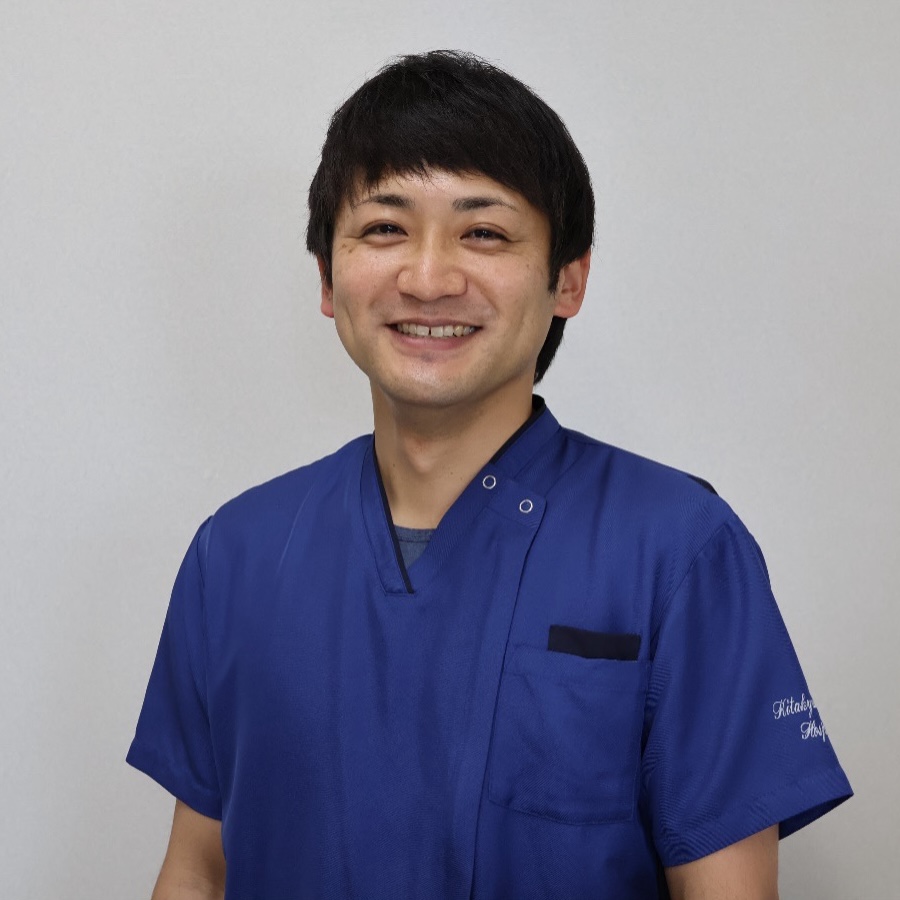- インタビュイー:音地亮さん
- インタビュアー:脇坂成重
第2部 「自分らしく、理学療法を続けるために」
■ 理学療法士を目指したきっかけ
理学療法士を目指したきっかけを、教えていただけますか?
よくある理由かもしれませんが、祖父が脳梗塞になったことが大きなきっかけです。中学生の頃でしたね。そこで初めてリハビリという仕事を知りました。実は姉がST(言語聴覚士)の仕事をしていて、リハビリに関わる仕事に身近な環境もありました。
特別に「これがやりたい!」という明確な目標があったわけではなく、祖父のリハビリを見たことで「じゃあ自分もやってみようかな」という感覚で理学療法士の道に進みました。
■ 教育の現場と現場復帰
音地さんは臨床から一度教育の現場に行かれたこともありますよね。どんな経緯だったのでしょうか?
急性期病院でずっと臨床をしていて、4~5年目から「もっと勉強しないと」と思い始めて、8年目くらいに異動の話が出ました。家庭の事情もあって、関東への転勤は難しく、学校教育の道を選びました。
ただ、学校の先生になりたいという強い志望があったわけではなく、「経験としてやってみようかな」くらいの気持ちでした。実際にやってみると、授業以外の生活指導が想像以上に多くて、正直、自分には向いてないなと早々に感じました(笑)
それでも、大学院に行くきっかけになったり、教え方を学べたりと、貴重な経験になったのは間違いありません。2年間の契約が終わったら、すぐに現場に戻りました。
■ 内部障害に魅せられて、探求し続ける理由
今は内部障害領域でご活躍されていますが、最初に興味を持ったのはどんなきっかけだったのでしょうか?
1年目のときに、5年目の先輩が内部障害を得意とされていて、その方について学んだのが最初です。寝たきりの患者さんの呼吸介助を行い、痰がごっそり取れて状態が改善するのを目の当たりにして、ものすごい衝撃を受けました。
「理学療法って、こんなに即効性があって面白いんだ」と思ったんです。それから手術後の急性期患者さんも担当し、自然と内部障害領域に関わり続けるようになりました。
そこから今のように専門的に取り組むようになったのは、何かきっかけがあったのですか?
4~5年目の頃ですね。運動器や中枢神経系はいわゆる花形で携わっている人口も多く、既にたくさんの研究成果が報告されている分野ですが、内部障害はまだ未開拓の部分が多いと感じました。もともと興味があったことに付随して、ここなら自分でも入り込める隙間があるかもしれない、という下心もありました(笑)。
でも結果的に、その直感は当たっていて、研究のフィールドも広がり、内部障害領域での活動にどんどんのめり込むことになりました。
■ 現在の立場と現場への想い
現在は理学療法士長に就任されていますが、今も現場に立たれているんですよね?
そうですね。課長が上にいるので、自分はまだまだ臨床業務がメインです。割合で言えば、臨床8割、管理業務2割くらいですね。
現場に立ち続けているのは、正直マンパワー不足の問題もありますが(笑)、自分自身が臨床で得られる気づきを大切にしているからです。患者さんを診ているからこそ、研究にも活かせるし、後輩たちに伝えられるものもあると思っています。
臨床に立てない管理職の方もいらっしゃると思います。そうした立場の方々に対する想いはありますか?
難しい質問ですね。自分もゆくゆくその立場になった時にどうすれば良いのだろうと考える立場と年齢になってきました。トップになると比重がマネジメントメインになるため、そのための勉強もたくさんしていかないといけないと思います。ただ、その時は臨床に即した研究は難しくなるけれど、システマティックレビューなど別の形で研究を続けたいと考えて、今はその下地を細々と作っています。
結局、現場に立てなくても、自分が熱中できるものを追求し続ける姿勢を後輩たちに見せることが大切だと考えています。臨床でなくても、学会活動や講師、研究など、自分の役割で背中を見せ続けたいですね。
Profile
音地亮さん
2005年に福岡新水巻病院入職。その後回復期病院や養成校の教員を経て、2019年に現在の北九州市立医療センターに入職。2025年4月より理学療法士長就任。
九州栄養福祉大学非常勤講師。
九州大学大学院 修士課程修了。
日本がん・リンパ浮腫理学療法学会、日本呼吸理学療法学会の評議員。
福岡県理学療法士会学術誌編纂部部長。日本理学療法士協会代議員。