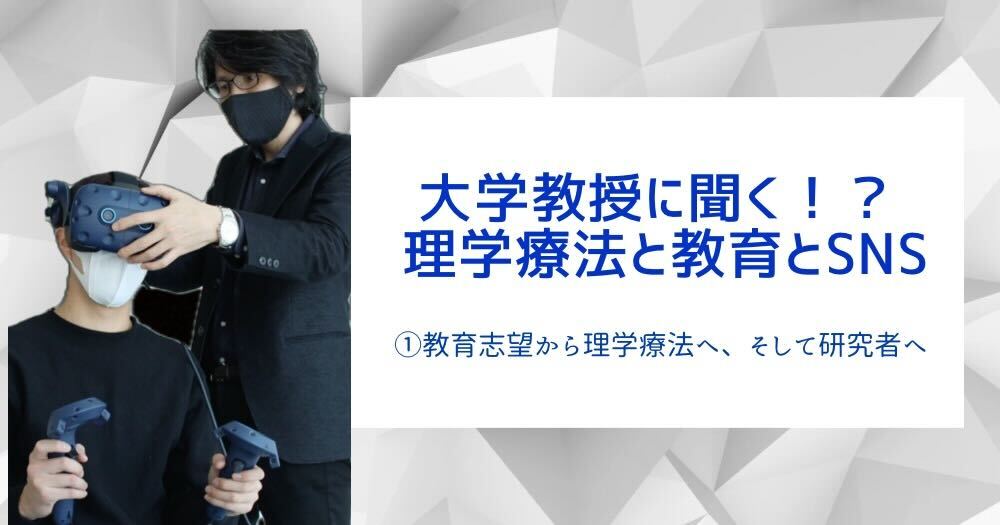教育志望から理学療法へ、そして研究者へ
本日はよろしくお願いいたします。インタビューの前に、ちょっと確認したいことがございまして。玉利先生がこのFUree worKUの事業に共感いただいているということを聞いているのですが。笑
事実ですね。笑 とても先進的な取り組みをされているなと思って記事もいくつか拝見させていただきました。
FUree worKUのコンセプトはご存知いただけていると思いますが、本日もなかなか聞けないお話を伺いたいと思っています。
まずは理学療法士になったきっかけについて教えてください。
元々は理学療法士になりたいとは思っていなくて、大学時代は教育学部だったんですよ。教育って自分が学んだことを教えるわけですが、教えることで自分もまた新たに学んでいるという連関性にすごく興味があったんです。
大学時代から、教員路線の学問を学ばれていたんですね。
そのなかで、大学3年のときに運動生理の研究室を選んだんですよね。その教授は水中運動と心拍数の関係なんかの共同研究を行っていて、かたや私はストレッチの効果を筋電図で見たりしていて、その中で理学療法士と出会ったんです。
そこが理学療法士との接点になるわけですね。
そうですね。そこで出会った理学療法士の知識の深さや理路整然と説明してくださる姿に衝撃を受けました。当時は理学療法士に興味があるくらいでそのまま教育学部を卒業したのですが、そのあと「やっぱり理学療法士になりたい」と思って養成校へ入学しました。
当時出会った理学療法士の影響が大きかったわけですね。
そうです。養成校へ入学してからは、理学療法士になって陸上選手のトレーナーをしたいというモチベーションだったんです。今ではまるで違う内容のお仕事をさせていただいてますが。
トレーナー・・・。先生のイメージからは想像がつかないですね。
いつから、現在行われている脳画像の研究テーマへ興味が向いたのでしょうか?
いくつかポイントはあるのですが、1年目に就職した職場で、その年の5月の全国学会に行かせて頂いたんですよね。そこで初めて見る世界に衝撃を受けたんです。正直、知識がないので発表を聞いてても何も分からないのですが、そこで脳卒中患者を対象とした動作解析の発表を聞いて、「これはすごい!」と思って、2年目には動作解析ができる職場に転職したんです。
行動力がすごいです。でも・・・先生の研究テーマって脳画像の研究が主で、あまり動作解析のイメージがないのですが・・・?
おっしゃる通りで、私はいわゆるバイオメカニクス(動作解析)の研究をしたくて転職をしたんですが、その後、教員になるタイミングでバイオメカニクスの研究を行える職場環境が失われてしまったんですよね。
なるほどー。教員になったことでバイオメカニクスを行えるハード面が失われたと。
ただ、バイオメカニクス研究ができないからといって何も研究をやらないわけにはいかないですから、なるべくお金を使わずにできることがないかなという点や、それまで脳卒中患者の動作を運動学や運動力学の視点からしか見ていなくて、脳機能の視点が足りていなかったんですよね。なので、この機会に脳画像の勉強をしてみるかという理由から今の研究テーマに行き着きました。
そんないきさつがあったとは知りませんでした。自分が興味がある研究はできない環境になったとしても、なにか別の研究ができないかと模索されている辺りが、研究者気質なのかなと思いました。
単純に疑問を追求したり、調べたりすることが好きなんだと思います。
今のお話しを聞いて思うのが、偶然に偶然が重なって脳画像という研究テーマに行き着いていらっしゃいますが、そこから長くそのテーマで研究をされていますよね。そこまで長く同じテーマで脳画像の研究を続けられる面白さとは何ですか?
それは、脳が分からないことが多いからではないでしょうか。以前はMRIで脳の画像は取れても、その解析技術が進んでいなかったのですが、私が興味を持ち始めた頃にはすでに様々な技術が発展していました。面白いと思っているところは、脳画像だけみれば歩けないと思われる患者さんであっても、実際には歩ける人も臨床には沢山いらっしゃいますよね。それは脳の可塑性を表していてそこに面白さを感じたんです。
確かに脳画像と臨床症状のギャップは現場で働かれているリハビリテーション職は感じることが多いですよね。
なので、最初は構造解析ですね。つまり脳の構造がどうなっているかを調査していましたが、同時に機能解析も行うという試みを始めたんです。
なるほどー。構造解析だけでは実際にどの程度患者さんが動けるかを捉えることができないからということですね。
そうなんです。今でこそ脳卒中患者さんの脳画像解析をさせていただいていますが、当初研究を行っていた病院では脳卒中患者さんが少なく、パーキンソン病患者さんの脳画像解析を中心にしていました。
どのタイミングで脳卒中患者さんの解析をすることになったのでしょうか?
ひと言で言えば、桜十字福岡病院の遠藤先生との出会いが全てですね。
もともと実習生の受け入れをお願いしにいったのが初対面だったのですが、そこで私がしたいことを受け入れてくださり、脳卒中患者さんの脳画像研究ができるように調整してくださったんです。
初対面からのスピード感がすごいですね・・・。
遠藤先生の考えは、病院が研究者や企業と連携し、意見交換しながら新しいものを生み出すプラットフォームとなるべきというもので、遠藤先生が柔軟性や先見性に優れていらっしゃることが大きな要因でした。遠藤先生との出会いがなければ今の私はないと思います。
桜十字福岡病院に属する桜十字先端リハビリテーションセンターには、工学の研究者も医療系の研究者も参画していて、さらに大学の教員も多数参画しています。桜十字先端リハビリテーションセンターでそれぞれの専門分野が交わり、新しいアイデアが生まれるようにという考えも基盤となっていて、実際に多数の共同研究が行われています。遠藤先生と、その考え方を持つ桜十字福岡病院の集団性と柔軟性がなければ、これは実現できなかったと思います。
やや玉利先生の話題からは逸れましたが、そもそも研究者として突き抜けていなければ今のような出会いや環境にも巡り合うことができないのだなと思いました。
改めて研究者としての玉利先生の凄さを感じました。先生は謙遜されるでしょうが。笑
いえいえ。笑
私はほんとに桜十字先端リハビリテーションセンターという大きな船に乗せて頂いているという感覚でやらせていただいていますので。笑